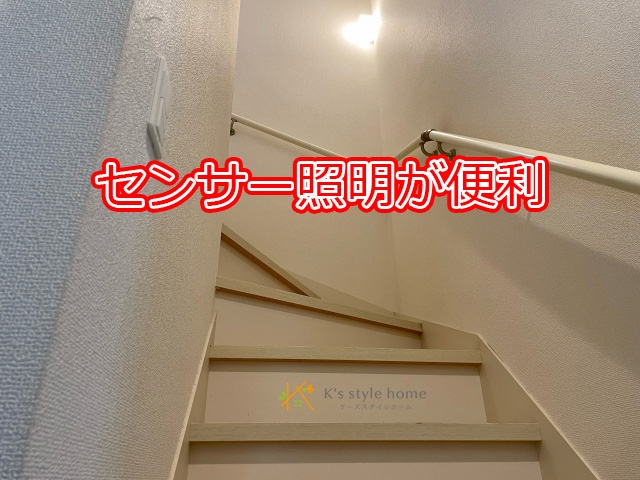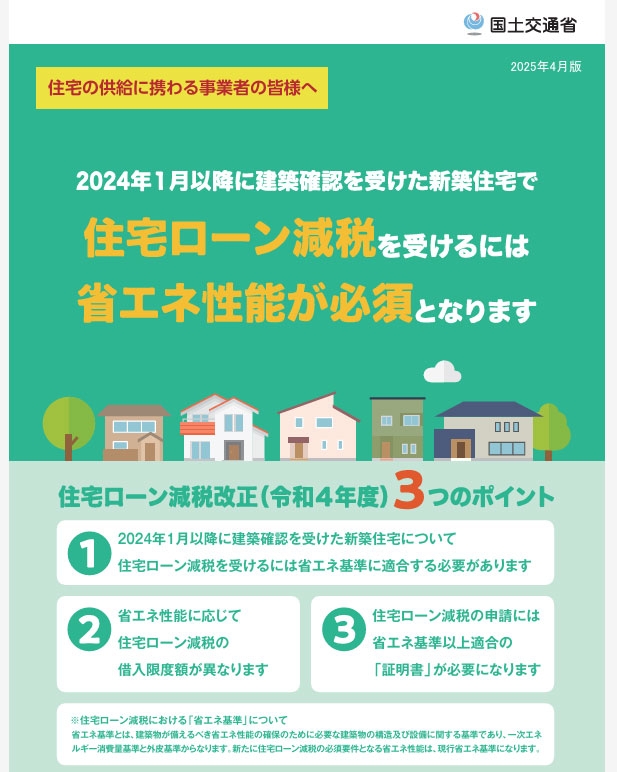新築住宅の湿気対策
連日雨ですね。四国地方まだ梅雨入りしてないはずですが、なんかじめじめしているスタッフMです。
我々は愛媛県西条市を中心に新築一戸建てを手掛ける建設会社「ケーズスタイルホーム」です。

さて、この時期(梅雨時期)に気になるのが、湿気対策ですよね。
もちろん、お家を建てる側の我々建設会社もしっかりこのことは考えております。
本日は、我々が新築で家を建てる際にしている対策をご紹介しますね。
1、適切な断熱と気密
目的:結露の防止と室内外の温度差を緩和。
対策:
高性能な断熱材を採用(セルロースファイバー、ウレタンフォームなど)。
隙間の少ない施工で気密性を確保(特にサッシまわりや配管まわり)。
気密シートを施工して湿気の侵入を防ぐ。
2、 換気システムの導入
目的:湿気を強制的に排出し、室内の空気を常に新鮮に保つ。
対策:
24時間換気システム(第1種・第3種換気)を導入。
水回り(浴室、脱衣所、キッチン)の局所換気も強化。
室内の空気が滞留しないよう、空気の流れを設計段階で計画。

3、防湿シート・防湿層の設置
目的:床下や壁内に湿気が入り込むのを防ぐ。
対策:
床下に防湿シートを敷設(ポリエチレンフィルムなど)。
土間コンクリートの下や基礎周囲にも施工。
壁内にも防湿層を設けることで内部結露を防止。
4、床下換気・基礎断熱
目的:床下にこもった湿気を排出して腐朽やシロアリを防止。
対策:
通気基礎を採用して自然換気。
もしくは基礎断熱+床下エアコンなどで空調管理。
床下点検口を設置し、定期的な確認が可能な構造に。

5、屋根・外壁の通気層設計
目的:壁内や屋根裏の湿気を逃がす。
対策:
外壁の内側に通気層を設け、壁体内結露を防ぐ。
屋根の通気構造(棟換気、軒裏換気)で熱と湿気を放出。
以上、個別相談や、設計時にもちろん上記のようなことは丁寧に提案・説明させていただきます。ご安心ください。
まず新築を考えたら個別相談にお越しください。お待ちしております。